
・佐々木 純一 [ 名誉院長/産婦人科部長 ](筑波大学医学群 臨床教授)
| 日本産婦人科学会専門医、母体保護法指定医、東京医科歯科大学臨床教授、 茨城県立医療大学客員教授、茨城県体育協会スポーツ医科学委員会委員
|
・喜多川 亮[ 科長 ]
| 日本産婦人科学会認定専門医 |
・大原 玲奈[ 科長 ]
| 日本産婦人科学会認定専門医、 日本産婦人科学会産婦人科指導医、日本周産期医療・新生児医学会周産期専門医(母体・胎児) |
・髙橋 賢司[ 科長 ]
| 日本産婦人科学会認定専門医 |
・平澤 亮子[ 医長 ]
・薗部 茜
・山中 詩織
・成田 さくら
・非常勤医師 吉木 尚之
・非常勤医師 市川 雅男
・非常勤医師 加藤 薫
・非常勤医師 中尾 仁彦
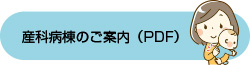 |
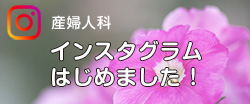 |
 |
当院は地域の中核病院として、妊娠・出産、婦人科疾患のほとんどの領域をカバーしております。
| 当院で受診、出産される方へ新型コロナウイルス感染症対応について | |
| 妊娠中の乳がん検診について |
〈入院診療〉
妊娠悪阻、切迫流早産、妊娠高血圧症候群、合併症妊娠(糖尿病合併妊娠など)等の入院加療を行っております。
6階フロア全体を産科病棟専用病棟にあてており、24時間助産師が病棟に常駐しております。また、休日や夜間でも当直医師が分娩に対応できるようになっております。
 |
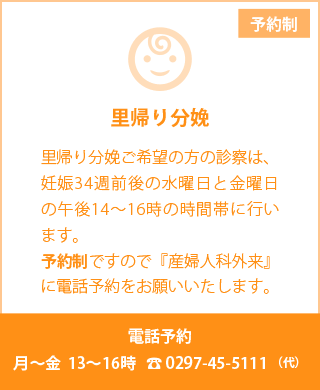 |
|||
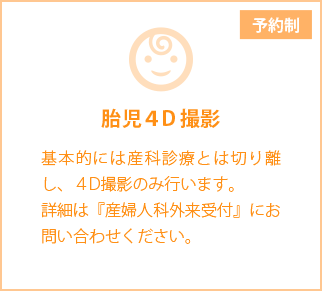 |
胎児4D撮影は予約制で水曜日、金曜日の午後に行っておりますが、写真撮影のみ(有料)は妊婦健診受診中にも行っております。赤ちゃんの向きにより、良く映らないこともあるため、毎回4D撮影を行うわけではないこと、必ず撮影できるとは限らないことをご了承ください。
|
| 写真撮影 (妊婦健診受診中に実施 当院受診の方のみ) |
|
| 白黒撮影 | カラー撮影 |
| 無 料 | 1枚につき 500円 |
| ○ | 妊婦健診受診中での写真撮影は非課税となります。 |
| ○ | 妊婦健診の補助券は使用することが出来ませんので、予めご了承ください。 |
| ○ | 妊娠12週目以降撮影が可能です。 |
初回検査時 → 24週頃 → 34週頃 → 37週以降 に行います。
妊婦一般健康診査受診票 をお持ちの方
県内で交付された妊婦一般健康診査受診票をお持ちの方は、下記の健診費用が助成されます。 (※他県交付の場合は金額が異なります。)
| ・ | 初回検査 血液型・梅毒・B型肝炎ウイルス・C型肝炎ウイルス・エイズウイルス・風疹・貧血・血糖・トキソプラズマ・水痘・甲状腺刺激ホルモン・子宮頸癌細胞診・不規則抗体・成人型白血病ウイルス |
| ・ | 24週時検査 貧血・50g糖負荷血糖・クラジミア |
| ・ | 34週時検査 B群溶レン菌検査 |
| ・ | 36週時検査 貧血・不規則抗体・NST ※ |
| ・ | 40週以降 NST ※ |
| ※ | NSTとは 赤ちゃんの心拍数と子宮の収縮の状態を調べる検査です。この検査で赤ちゃんが元気かどうかがわかります。 |
上記の検査項目の他に必要とされる検査を行った場合は、検査分の費用がかかります。
パパママクラス下記の時間に行っております。16週以降に『産婦人科外来受付』でお申し込みください。
※各市町村でも行っています。当院で受講できない方はそちらで受講してください。
|
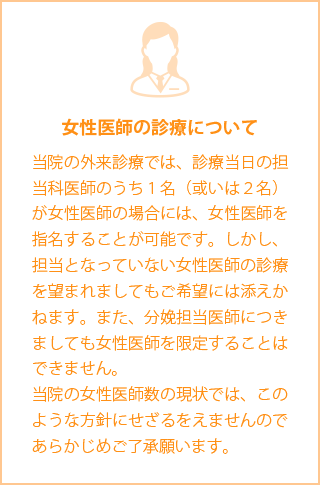 |
《入院保証金に関するお知らせ》
分娩費用のお支払い方法が変更となります。
入院保証金として、妊娠20週10万円、妊娠30週10万円をお預かりすることになりますので、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
里帰り分娩をご希望される方は、お電話にてお問い合わせください。
《入院保証金》
※「入院保証金」は出産時入院費用の一部に充当させていただきます。
※健康保険未加入、直接支払制度を利用しない場合、入院保証金は60万円となります。
《出産費用》
平成22年の改訂から、出産基本料金は 約54万円 となります。
※上記の金額に別途個室料金がかかります。
《個室料金》
当院6階フロアが産科専用病棟となっております。お産をされる皆様には、入院生活を快適にお過ごしいただけるよう原則個室を用意してございます。(個室料金を頂くようになります。)
料金についてのお問い合わせは、1階入院窓口にてお願いいたします。
〈 産科病棟個室料金(非課税)〉
| 本館 | 特別室/1室 | 12,000円(1日) |
| 個室 /6室 | 10,000円(1日) | |
| 個室 /1室 | 5,000円(1日) | |
| 新館 | 個室 /7室 | 10,000円(1日) |
特に理由のない限りは自然分娩です。分娩室ではブドウ糖の点滴をはじめますが、分娩時の予期せぬ多量出血に備えるためです。また、分娩直後には子宮収縮をよくする薬を点滴します。子宮の収縮は分娩時の出血量に大きな影響を及ぼします。
◎陣痛が来る前に破水をした場合
抗生物質を使用して約1日の間自然に陣痛が起きてくるのを待ちますが、
陣痛が起きてこない場合には、陣痛をおこす薬を使います。
◎41週付近になっても陣痛が起きてこない場合も、入院していただきお産にします。
◎骨盤位は、帝王切開です。
◎前回帝王切開の方も、帝王切開です。
[ご留意点]
※分娩担当を、女性医師に限定することはできません。
※当院は県立医療大学、筑波大学、県立中央看護専門学校の実習病院となっておりますので、
看護学生、研修医が診療に立ち会うこともあります。ご協力をお願いいたします。
聞きたいこと、疑問な点などありましたら遠慮なくご相談ください。
《授乳》
原則として母乳をあげていただきます。足りない分はミルクを足すことにしていますが、母乳だけで頑張りたい方はご相談ください。
《母児同室》
お産の翌日の11時から、母児同室になります。
初日から母児同室を希望される方はご相談ください。
例年、この時期に問題となるのは、4月1日までに分娩するか、4月2日以降に分娩するかで、お子さんの学年が変わることです。患者様の希望により、「早く生ませてほしい」あるいは「遅く生ませてほしい」との要望が出てきます。
当院では、医学的な理由以外で分娩日を早くしたり遅くしたりするような人為的なことは行っておりません。したがって上記のご要望にはお答えできません。
分娩を希望の日に行いたい方には、他の病院をご紹介いたしますので、他の病院とご相談の上お早めにお申し出ください。
※当院では希望をかなえてくれる病院を斡旋することはできません。
お母さんと赤ちゃんのために、面会は短くお願いします。
〈面会時間〉
平日・土曜日/ 15:00 ~ 20:00
日曜・祝祭日/ 10:00 ~ 20:00
お産をした次の日を1日目と数え、4日目に退院診察をして5日目に退院の予定です。
《書類》
分娩費請求等の書類は、ナースステーションの受付で申し込んでいただきます。
入院したらお申し出ください。
《分娩費用》
入院してその日のうちに分娩となって5日目に退院される場合で約60万円です。
当院には、NICUがありません。当院での出産が可能なのは、妊娠35週以降、児体重2000g以上となっております。この基準を満たさない場合には、母体搬送をさせていただく場合があります。
当院では、羊水検査は行なっておりません。筑波大学病院などを紹介させて頂いています。
検査可能な時期は妊娠18週以前ですので、ご希望の方は早めにご相談ください。
また、母体血液検査で染色体異常の確率を判定するマーカー検査『クワトロテスト』も行っておりません。
平成30年8月1日より、人工妊娠中絶を開始いたします。ただし、何らかの合併症があるために開業医での実施が困難な場合、あるいは妊娠中期中絶(妊娠12週~22週未満)の場合とさせていただきます。
当婦人科では、良性腫瘍、婦人科癌、骨盤臓器脱、不妊症、更年期障害、避妊など、ほとんどの領域の診療を行っております。
|
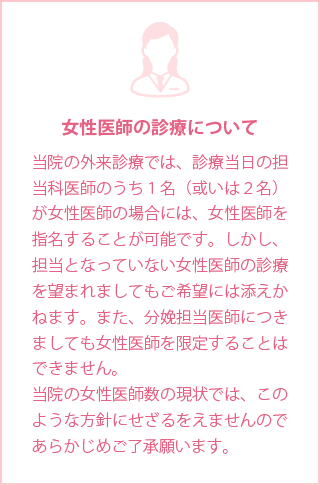 |
自覚症状が強く(月経量が非常に多い、月経痛がひどいなど)本人の苦痛が大きい場合、筋腫が著しく大きな場合、筋腫が大きくなるスピードが速い場合などは手術をお勧めしています。
しかし、自覚症状が軽い場合、筋腫があまり大きくない場合、閉経が近い場合などは手術をせずに様子を見ることも多くなっています(筋腫は閉経後は大きくならず、かえって萎縮して小さくなっていくことが多いからです)。
(1)子宮筋腫の薬物療法
子宮筋腫に対する薬物療法はいくつかありますが、残念ながら、筋腫を根治させることはできません。薬物療法の目的は、
1.自覚症状を軽減させる
2.筋腫が増大するスピードをゆっくりにさせる
3.手術に際し、貧血を改善したり筋腫を小さくすることによって手術を容易にする
4.閉経までの時間稼ぎ
などです。実際の治療法としては、偽閉経療法、漢方療法などがあります。
(2)子宮筋腫の手術療法
子宮筋腫の手術療法には、大きくわけると筋腫のみを摘出するやり方(筋腫核出術)と、子宮を全部とるやり方(子宮全摘)があります。
筋腫核出術は、これから子供を生みたい方や、子宮の温存を強く希望される場合に行う術式です。長所としては、子宮が温存されることですが、短所としては、術中の出血が多くなりやすいこと、筋腫の再発が多いこと、などがあげられます。
子宮全摘は、すでに子供を生み終わった方で、子宮の温存を希望しない方の場合に行われることが多い術式です。この術式の長所は、筋腫の再発がないこと、子宮癌の心配がなくなることなどがありますが、逆に短所としては、子供が産めなくなってしまうことがあげられます。子宮全摘をおこなうと生理はなくなりますが、卵巣を同時に摘出しなければ女性ホルモンは卵巣から分泌されますので更年期症状が出現することはありません。ただし、もともと更年期にさしかかっている方の場合には、手術をやったやらないにかかわらず、更年期症状が出現することがあります。
実際の治療法としては、腹式・膣式子宮全摘術、開腹子宮筋腫核出術(子宮筋腫のみ摘出する方法)、腹腔鏡下子宮筋腫核出術、腹腔鏡補助膣式子宮全摘術、子宮鏡下筋腫核出術(子宮内に突出しているタイプの筋腫の場合)などがあります。最近では腹腔鏡下手術もよく行われるようになってきましたが、大きなものや数が多い場合は開腹手術で行います。
(3)子宮筋腫の子宮動脈塞栓術/超音波焼灼療法
子宮動脈塞栓術は、カテーテルを挿入して子宮に栄養分を供給している動脈に塞栓物質をつめて血流を遮断し、兵糧攻めにする方法
超音波焼灼療法は、体外から超音波をあて、筋腫に焦点を当て焼いてしまう方法
体に傷がつかないのがよい点ですが、両方法とも保険がききません。※当院では行っておりません。
良性の卵巣腫瘍のことです。良性の腫瘍という点では子宮筋腫と同じです。子宮筋腫では必ずしも手術をお勧めしませんが、卵巣のう腫の場合には、手術をお勧めします。その理由は、子宮筋腫が悪性化することはほとんどないのに比べ、卵巣のう腫の場合には、時々悪性化することがあるといわれているからです。残念ながら薬物療法はありません。
卵巣のう腫の手術療法
子宮筋腫の場合と同様、卵巣のう腫の場合にも、のう腫だけをとる手術(のう腫核出術)と、卵巣全体をとる術式(通常は卵巣と卵管と同時に摘出し、付属器摘出といいます)があります。のう腫核出術は、若い方、のう腫が比較的に小さい方の場合にお勧めしています。のう腫が大きい場合や悪性かもしれない場合は、付属器摘出をお勧めします。卵巣は全摘しても、もう片方の卵巣が機能を代償しますので、女性ホルモンの量が半分になってしまうことはありません。手術の方法は、開腹手術と内視鏡による手術(腹腔鏡下手術)があります。開腹手術は手技が容易であること、下半身麻酔(腰椎麻酔や硬膜外麻酔)ですむことなどが長所です。ただし、傷がやや大きい点が欠点です。腹腔鏡下手術は傷が小さく、術後の回復が早く早期の退院が可能であることが長所ですが、全身麻酔が必要なこと、手技がやや難しいこと、のう腫の内容を腹腔内に漏らす可能性があることが短所です。
子宮癌には子宮の出口(頚部)にできる子宮頚癌と子宮の内部にできる子宮体癌があります。昔は欧米では子宮体癌が多く、日本では子宮頚癌が多かったのですが、最近では生活の西欧化に伴い、日本でも子宮体癌が増加しています。また、最近では若い人の子宮頚癌が増加してきています。子宮頚癌の主な症状は性交後出血ですが、早期の場合にはほとんど症状がありません。子宮癌検診で発見が可能なので、定期的な検診をお勧めします。
子宮体癌の主症状は閉経後出血ですが、頚癌の場合と同様、早期には症状がない場合もよくあります。通常の子宮癌検診で発見されることもありますが、特別な検査を行わないと発見できない場合のほうが多いのです。月経の周期がばらばらな方、時々不正出血がある方などは体癌の検査も行っておいたほうが安心できます。
(1)子宮頚癌の治療
1.手術療法
第一にお勧めする治療法です。治癒率がほかの治療法よりよいのでお勧めしています。もちろん、臓器を摘出するわけですから、それに伴った合併症や障害が起こることもあります。特にリンパ節を摘出するような拡大術式の場合には、膀胱に分布する神経を部分的に切断せざるを得ないため、尿がたまった感じがわかりにくくなったり、排尿がスムーズに行かなくなったりすることがあります。術後に足がむくんだり、リンパのう胞と呼ばれるリンパ液のたまりが足の付け根あたりに発生することもあります。子宮癌でも、早期癌の場合には子宮の出口の部分だけを摘出して子宮本体を温存したり、子宮筋腫とおなじような簡単な手術でも充分治るとされていますので、上に書かれたような障害はおきません。
2.放射線療法
放射線療法は頚癌の場合には手術療法とならびよく行われる方法です。手術療法に近いくらいの治癒率があります。体に傷がつかないのが最大の長所です。短所としては、近接臓器である直腸や膀胱にも放射線があたってしまうので、下痢になったり、血尿や血便が出現することもあります。放射線療法は手術療法に比べ体に与えるストレスが少ないので、高齢の方、合併症の多い方などによく行われています。放射線療法は単独で行われることもありますが、術後の再発防止のために手術後に追加して行われることもあります。当院には放射線治療の設備がありませんので、筑波メディカルセンター病院や筑波大学病院、慈恵医大柏病院などに依頼して放射線治療を行っています。
3.化学療法
単独で行われることは少なく、他の治療法と併用して行われることが多い治療法です。抗がん剤の副作用に注意する必要があります(白血球減少や血小板減少、吐き気、腎臓障害など)。
【子宮頚癌予防ワクチン】
子宮頚癌予防ワクチンの接種を開始しました。全部で3回接種(初回、10ヵ月後、60ヵ月後)します。約75%の子宮頚癌を予防できるとされていますが、100%の予防をめざすには毎年の子宮癌検診(細胞診)との併用が効果的です。
(2)子宮体癌の治療
1.手術療法
子宮頸癌の場合と同様、まず第一にお勧めする治療法です。治癒率が他の治療法に比べ高いのが特徴です。手術のやり方は子宮頸癌の場合と大体同じですが、子宮の内部に癌が発生していますので、子宮を温存することは特殊な場合を除いては不可能です。また、膀胱機能に対する手術の影響が頸癌の手術に比べ小さいこと、拡大術式の場合に、臍の上のほうまで切開し、リンパ節を摘出することがある点などで頸癌の場合とやや異なります。
2.放射線療法
子宮頸癌にくらべ、子宮体癌では放射線療法の効き目は今ひとつです。しかし、合併症の多い方や高齢者で手術が危険と考えられる場合にはお勧めします。術後の追加療法として選択されることもあります。
3.化学療法
単独で行われることは少なく、他の治療法と併用して行われることが多い治療法です。抗がん剤の副作用に注意する必要があります(白血球減少や血小板減少、腎障害、吐き気、脱毛など)。
4.ホルモン療法
若い未婚の方、術後の追加療法として行われることが多い治療法です。癌を根治させることは難しいのですが、進行を食い止めることができる場合があります。まだお子さんがいない初期癌の若い方の場合には、ホルモン療法で進行を食い止め時間稼ぎをし、その間に妊娠・出産をしていただき、その後に手術をして子宮を摘出することができる場合があります。ホルモン療法で使用される薬は黄体ホルモン系の薬ですが、血栓症ができやすくなる副作用があり注意が必要です。
卵巣癌は日本人では比較的に少ない癌ですが、最近増加してきています。予後が悪いのが特徴ですが、その最大の理由は早期発見が難しいからです。腹痛があったり腹部に腫瘤を触れる場合もありますが、これといった自覚症状もないのに、かなり進行した状態になってしまっていることもあります。このように自覚症状が乏しいため、早期発見がなかなか難しい癌ですが、子宮癌検診をうけるついでに卵巣も同時に調べてもらうようにするのがよいと思います。近親者で卵巣癌の方がいる場合は、リスクが高くなることがありますので、ときどき婦人科を受診されるようお勧めします。
卵巣癌の治療
1.手術療法
基本的な治療法です。両側の卵巣・卵管、子宮、骨盤内~腹部のリンパ節、大網(胃や腸からたれさがっている脂肪の垂れ幕のようなもの)、虫垂を摘出します。摘出する理由は、これらの臓器に癌が転移しやすいからです。初期癌で、まだ子供のいない方の場合には、子宮と片側の卵巣を温存する術式が選択されることもあります。膀胱機能に影響が出ることは少ないのですが、リンパ節を摘出するので、術後に足の付け根にリンパ液がたまったり、足がむくんだりすることがあります。
2.化学療法
抗がん剤を使用する方法です。婦人科の他の部位の癌に比べ、奏効率が高いのが特徴です。抗がん剤の副作用として、白血球減少、血小板減少、手足のしびれ、腎障害、吐き気、脱毛、などがあり、注意が必要です。以前に比べ、使用できる抗がん剤の種類が増え、選択肢が多くなってきました。
3.放射線療法
他の治療法に比べ、選択されることが少ない治療法です。何らかの理由により手術が行ないにくい状況の場合などに選択されます。
最近増加しているといわれています。若い方にも発見されるようになってきました。子宮内膜症という病気は簡単に言えば、子宮やその周辺、卵巣などに「血まめ」ができる病気です。
どうして「血まめ」ができるのかというと、通常は子宮の中にあり、月経のときに出血する子宮内膜が、なぜか子宮内以外のところに存在するため、月経の時にその場所でも出血するからです。
出血の出どころがないため、その血液は「血まめ」となって貯まっていきます。従って、月経がある状態では、子宮内膜症は次第に悪化していきますが、妊娠・出産・授乳などにより月経が止まっている状況下や、閉経後などでは次第に良くなっていきます。
子宮内膜症がやっかいなところは、「血まめ」ができるばかりではなく、その周辺に癒着を引き起こすことです。この癒着などにより、不妊症になりやすくなります。また、卵巣にできた子宮内膜症である卵巣チョコレートのう胞には、ある種の卵巣癌が発生しやすい点も問題です。
子宮内膜症の症状は、月経痛が激しいこと(月経困難症)が主なものです。性交痛や排便痛が症状であることもあります。
治療法としては、薬物療法(鎮痛剤による対症療法、偽閉経療法、ホルモン療法、漢方療法など)と、手術療法、卵巣チョコレートのう胞アルコール固定などがあります。薬物療法ではある程度子宮内膜症をよくすることはできますが、根治させることはできません。若い方、未婚の方には薬物療法や、卵巣チョコレートのう胞のアルコール固定が主として行なわれます。結婚後不妊の方では子宮や卵巣卵管を温存し、内膜症の部分だけを摘出し、癒着を剥離する保存的手術療法を行なうこともあります。すでにお子さんが何人かいるような方では、内膜症部分や卵巣を摘出することも行なわれます。
子宮筋層内に子宮内膜症が発生した子宮腺筋症に対しては、ホルモン療法(LEP、OC)、偽閉経療法、ホルモン付加子宮内避妊器具(IUS)などの治療を行っています。
10組の夫婦のうち、1組は不妊で悩んでいると言われています。当院では、一般不妊検査(ホルモン検査、クラミジア検査、卵管通気検査、子宮卵管造影検査、排卵の時期チェック、フーナー検査、精液検査、腹腔鏡検査など)をおこなっています。
治療としては、排卵時期推定によるタイミング指導、卵管通水、排卵誘発剤、ホルモン療法、配偶者間人工授精などをおこなっています。非配偶者間人工授精、体外受精、顕微受精は行なっておりません。
流産を繰り返してしまう不育症の場合には、膣細菌検査、クラミジア検査、ホルモン検査、子宮卵管造影検査、子宮鏡検査(必要時)、血液検査(凝固系検査・自己抗体検査・夫婦の染色体検査など)などをおこないます。
当院ではピル、子宮内避妊器具による方法をお勧めしています。いずれも保険はきかず、自費診療となります。
避妊用ピル
避妊用ピルはちゃんと服用していればほぼ100%避妊できますが、飲み忘れると妊娠する可能性がでてきます。また、連日服用しなければならない点が面倒です。さらに、性行為感染症を防ぐこともできません。
当院で採用している避妊用ピルは低用量ピルで、21日間内服・7日間休薬をくりかえすタイプと、内服持続タイプのものです。低用量なのでそれほど大きな副作用はありませんが、血栓症の頻度が増えるとされています。とくに35歳以上で1日15本以上タバコを吸っている方では要注意です。また、薬は肝臓で代謝されるため、肝障害がおきることもあります。上記に該当する喫煙者、血圧が高い方(140/90以上)なども処方出来ないことになっています。
ピルの内服を開始する前に、子宮癌・乳がんの検査をお勧めしています。また、長期的にピルを服用している場合には、時々副作用チェックのための血液検査(血液凝固検査、肝機能検査など)を行なうことにしています。
【性交後ピル】
性交後72時間以内に服用をはじめると、妊娠をある程度阻止することができます。
早めの服用の方が妊娠率が低くなると言われています。
※ピルは避妊を目的とした薬です。ピルの内服により、妊娠を避けることはできますが、
性行為感染症(クラミジア、梅毒、淋病、エイズなど)は防ぐことはできません。
これらの感染予防のためには、コンドームの併用が必要です。
子宮内避妊器具(避妊用ループ)
当院採用のものは、通常のもの、銅付加のもの、黄体ホルモン付加のものの3種類です。
避妊効果は95~99%といわれており、ピルに比べやや落ちる点が欠点ですが、一度挿入すると2~5年間くらいは交換不要なので、手間がかからないところが長所です。
避妊用ループを挿入する前には、子宮癌の検査(頚癌検査と体癌検査)をお勧めしています。ループを挿入すると、不正出血がおこることがありますが、癌による出血かループによる出血かの判別がつかなくなるからです。
子宮内避妊器具を交換せずに長期にわたって子宮内に留置したままにしておくと、抜去困難となったり重篤な細菌感染症がおこることがあるので定期的な交換をおすすめします。
検診券をお持ちの方は、健康増進部で受付してください。婦人科外来を受診される場合、ご希望での検診は自費となります。
当院は、茨城県の子宮癌精密検査指定病院となっております。
大体45~55歳にかけて、のぼせ、発汗、頭痛、腰痛、不眠、いらいら、だるさ、やる気がなくなる、など、多彩な症状が出てきます。更年期障害の原因としては、女性ホルモンの急激な減少、家庭環境の変化、もともとの性格的なものなどが複雑に絡み合って発症するといわれています。
治療法としては、以下に述べるホルモン補充療法と漢方療法、その他症状に対する対症療法があります。
ホルモン補充療法
更年期障害の原因の一つが女性ホルモンの減少なわけですから、それを補うことで症状の軽減を図ろうとするものです。女性ホルモンには2種類ありますが、片方のホルモンの投与だけでは副作用が出るので、両方のホルモン剤を組み合わせて処方するのが一般的です。ホルモン療法は、効果が出やすいことと、骨がもろくなるのを防止できるのが長所ですが、不正出血がでたり、血栓症になりやすくなったり、心臓病になりやすくなったり(外国のデータ)する点が問題です。
漢方療法
ホルモン療法に比べると副作用が少ないのが特徴ですが、効き方がマイルドです。薬がうまく合う人と合わない人があります。
無月経・月経不順
妊娠を目的としないのであれば、3ヶ月以内にそれなりのペースで月経が発来していれば、とくに治療の必要はありません。ただし、この期間を超えて無月経の状態が続いてくると、将来の不妊症の頻度が増えてきたり、骨がもろくなってきたりします。
月経困難症
はっきりした原因があり、月経痛がひどい場合(子宮内膜症や細菌感染や子宮の形態異常など)と、明瞭な原因がないのに痛みがひどい場合があります。若い人では前者が多いのです。治療法は鎮痛剤による対症療法が第一です。これでだめなら、ピルやホルモン剤を用いて、排卵を抑えるなどの治療が必要になってくることもあります。
月経前緊張症
欧米で多い病気ですが、日本ではあまり多くありません。月経の前1週間くらいからいらいらしたり、頭痛、頭重感、眠気、からだのむくみなどがあわられ、月経になるとこのような症状は治まってしまいます。治療法には対症療法やホルモン療法などがあります。